
こんちは、すぎ(@sugiblog)です。
今日も今日とてベストセラー本をご紹介します。
今回ご紹介する本は「FACT FULNESS」


2019年に発売されてから既に100万部を超える大ベストセラーになっている本書。
化物級のヒット作ですが、僕は最近まで読んだことがありませんでした。
何故かっていうと、本がめっちゃ分厚いから。
測ってみたら2.5センチもありました。
でもなんか気になる、と思い手を伸ばしてみましたが、予想以上に読みやすく何より面白かったです。
海外ベストセラーの和訳書って内容がなかなか頭に入ってこないことが多いのですがこの本は全くそんなことがなかったですね。
本書を読み終えたあと僕は、乾貞治並みにデータを意識していこうと決心しました。
▼こちらの記事でおすすめのビジネス本をまとめているのでぜひチェックしてみてください。
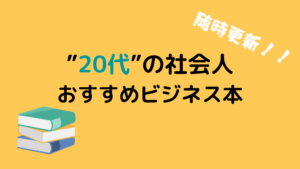
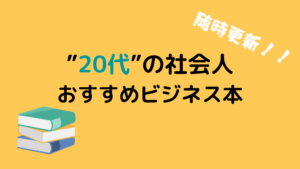
FACT FULNESSってどんな本?
本書が伝えているテーマは一貫して一つ。
「事実に基づき考えること」
多くの人ができていないようです。
一般的に人は本能的な思いこみをしていて、いかに世界を正しく見ることができていないかについて著者は警鐘を鳴らしています。
その思い込みとは具体的には下記のとおり。
- 分断本能
- ネガティブ本能
- 直線本能
- 恐怖本能
- 過大視本能
- パターン化本能
- 宿命本能
- 単純化本能
- 犯人探し本能
- 焦り本能
この10種類の本能が働き、物事に対して思い込みを生んでしまうとのこと。
本書ではこの本能の解説から始まり、本能がどのように作用して思い込みが生まれてしまうか述べられています。
生まれた思い込みに対して、データに基づく事実を用いて偏見をなくすことが可能になるわけです。
そうすることで必要以上に何かを心配したり、他者を傷つけるような言動をすることがなくなっていく。
これがいわゆる「FACT FULNESS」ってやつです。
よくソースあんの?とかいう言葉をネットで見かけますが、彼らの発言はあながち間違っていないのかも知れません。
事実やデータによる裏付けがあって初めて、経験や感覚といった個人的な部分が生きてくるってことですね。
また本書では世界に対する大きな誤解をわかりやすく解説してくれているので、単純に知識欲が駆り立てられて楽しみながら読むことができました。
自分が持っているイメージは果たして正しいのか?
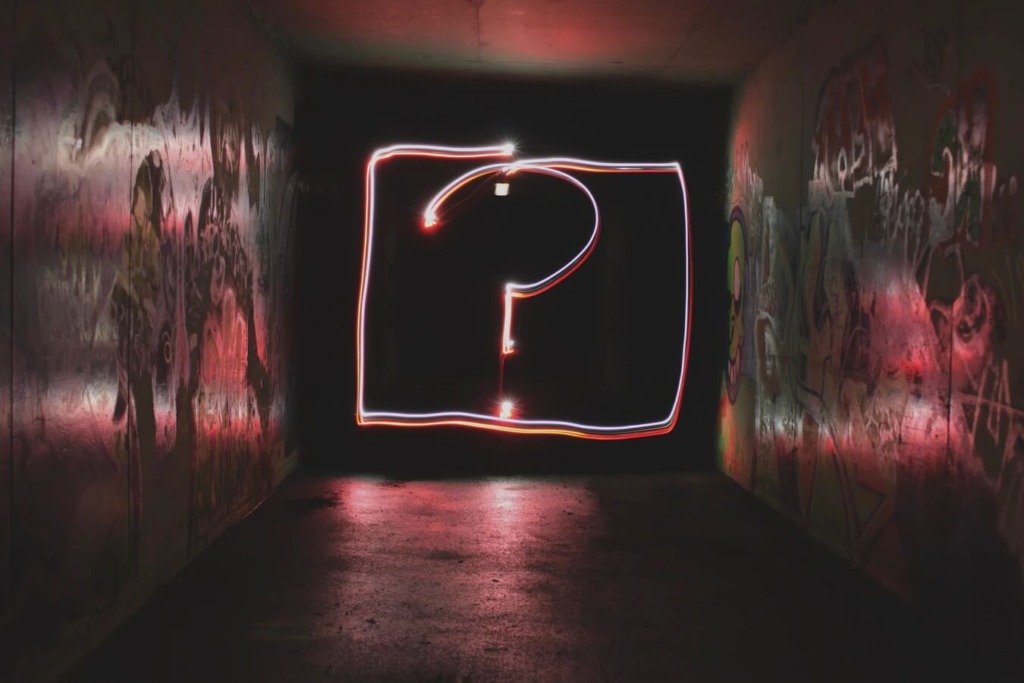
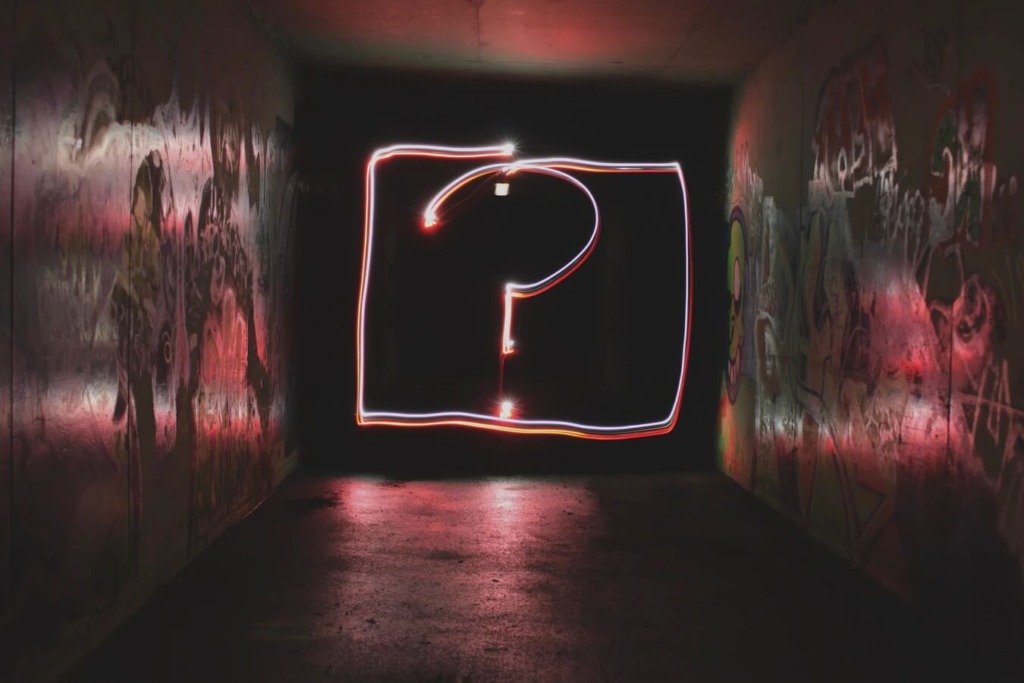
本書を読んでまずびっくりするのは、自分は驚くほど世界について何も知らないということです。
まず冒頭に世界に関する3択クイズが出題されます。
この正答率が悪いこと悪いこと・・・
著者はそのことについて、チンパンジーの方が世界のことをよく知っていると表現しています。



こいつ、完全に煽ってきてやがる・・・!
いやそれはただの確率論やん・・・っていうツッコミはグッと堪えて、確かに世界について何も知らない。
常日頃から、いかになんとなくのイメージで物事を捉えているかを思い知らされました。
普段の仕事に置いても、企画を提案する際に上司から「それってあなたの感想ですよね?なんかデータってあるんですか?」ってよく言われますよね。
本書ではあくまで世界の貧困や地球温暖化、女性の教育機会など、社会的な問題にフォーカスして思い込みの是正をしています。
でもこれって個人レベルの日常生活でも当てはまるんじゃないかって思いませんか?
普段自分がしていること(仕事やプライベートのあらゆる言動)に何かしらの思い込みやバイアスが働くことは避けられないと思います。
だからこそ少しでも根拠となるデータや客観的事実に目をやる習慣をつけていきたいと感じました。
感覚だけで生きると損するかも?
データや事実に基づくものの見方が大切って話は理解できる話です。
逆にそれができないと、どんな弊害があるのか考えてみました。
客観的事実やデータを完全に度外視して自分の経験則や感情論で語る人をみたことありませんか?
わかりやすい例で言うと有名なのが、「おれらの時代は〜、それに比べて近頃の若いもんは〜構文」です。
完全に自分の感覚で話してるよね?
この構文を繰り出す中年男性は確かに若い頃多くの苦労をしたのかも知れません。
いってる内容も一理あることもしばしば。一理は認めてあげましょう。
ただこの構文が若者に受け入れられないのは、中年男性の主張=世の中の真理にならないからです。
世の中の真理なんて言うと大袈裟ですが、とにかくそれが正解なのか間違っているのか判断できるほどの材料が整っていないケースがほとんどです。
自分の感覚だけで主張しても大体受け入れられていないか、腹落ちしないけど面倒だから話を合わせられているか、どちらかだと思われます。
それって一見、自分の意見が通っていたとしても全然ポジティブな状況ではないですよね。
感覚や経験則は個人の考えを示す上で重要なファクターですが、根幹にしてはいけない場合が多いです。
特にビジネスや社会問題に関する場面に置いては。
僕自身本書を読んでみて、もしかしたら自分も知らず知らずの内に思い込みで物事を捉えたまま決断や主張をしていたケースがあったかもなぁと思いました。
まとめ:データと感覚の両立が必要
最後に簡単に本書の内容とおすすめできる人をまとめます。
本書の内容
- 世の中の多くの人は思い込みに基づいて世界を見ている
- 思い込みを生むドラマティックな本能を理解し、克服する方法が解説されている
- 事実やデータに基づいて物事を見ることでより良く生きることができる
こんな人におすすめ
- 世界について、自分の理解度を確認したい人
- データや事実に基づく考え方が好きな人
- 普段感覚的に物事を判断して生きていると感じる人
感覚や思いはデータの上に成り立たせましょう。
著者自身も数字だけでは世界は見れないが、数字がないと世界は見れないと言っています。
どちらか一方に偏るのではなく、どちらの特性や利点を理解して物事を考えていければベストです。
情報過多の現代を生きる上で、データは比較的容易に手に入ります(正しいデータかどうかには十分注意しましょう)。
データに基づく客観的事実は大切ですし、何より知ることが新鮮で楽しいと感じられると思います。
そうして集めたデータに自分の意思感情を加えたブレンド思考を実践していきたいものです。
それじゃ、またねっ!
にほんブログ村ランキングに参加しています。応援宜しくお願いします!


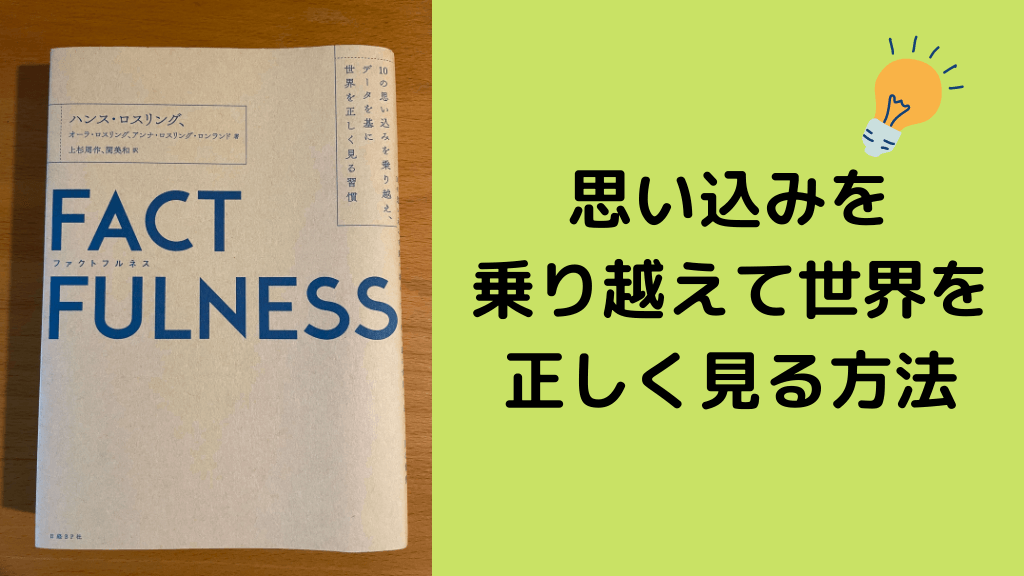

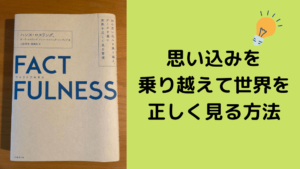
コメント