不朽の名著「人を動かす」
こんにちは、すぎです。
今回は自己啓発の教科書、「人を動かす」をご紹介していきます。

うーん、歴史と伝統の詰まったイケてる表紙ですな。
なななんと、1936年に初版が発刊されて以来現在に至るまでに累計1,500万部を売り上げている超ベストセラーです。
東京都の人口が大体1400万弱なので、この本は東京都民のバイブルと言えるでしょう。
人間関係のなんたるかが詰まっているこの本の偉大さと、読むことで何が得られるかについて紹介していきます!
この記事でわかること
- 「人を動かす」ってどんな内容の本?
- 実際に読んでみて感じたこと
- 日常生活にどう活かす?
こんな流れでご紹介していきますのでどうぞよろしくお願いします。
まずは基本情報をまとめます。
タイトル:人を動かす
著者 :デール・カーネギー
単行本 :346ページ
出版社 :創元社
発売日 :1999年10月31日(新装版)
価格 :¥358(Kindle版)
いや、kindle版安すぎだろぉぉ。
文庫版でも700円程度で購入できます。
この価格で人間関係の全てを垣間見ることができるなんて、感謝しかない(゚∀゚)
Amazonで見てみると単行本よりKindle版の方が安く買えるのでおすすめですよ。
Kindleデビューされていないなら、この機会にご検討されてみてはいかがでしょうか?
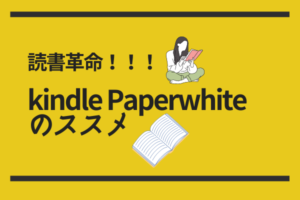
早速本題に入っていきましょー!
それでは、どうぞ!
「人を動かす」ちょこっと内容紹介
本書は5つのパートに分かれています。
- 人を動かす三原則
- 人に好かれる六原則
- 人を説得する十二原則
- 人を変える九原則
- 幸せな家庭をつくる七原則
いずれも人間関係を如何に上手く構築するかが根本のテーマになっています。
「原則」というと言葉は固いですが、内容は義務教育過程で誰もが学ぶような当たり前のことが多いです。
ただ改めてそれができているかと問われると迷いなくイエスと答えることができない原則も多々あります。
人の立場に身を置く
出典:人を動かす
これは「人を動かす三原則」の一つとして紹介されています。
こんなん当たり前の話やん?
って思うんですけど、日頃の自分の生活を振り返ってみると果たしてどうでしょう?
仕事は自分のタスクを処理することを優先しすぎていないか、家族への振る舞いは適切かどうか。
些細なことでも見直すべきポイントは見つかるかと。
こんな感じで単純な内容がほとんどですが、改めて言われるとなぁぁの連続でした。
全てできている人がもしいたらきっとその人は後光が差しているに違いありません。
一つ一つの原則が実例付きで解説されているので、イメージを付けやすく読めるのも特徴ですね。
また、基本的には各原則で独立しているので、自分の気になる部分から読み進めることもできますよ(゚∀゚)
 すぎ
すぎ洋書ならではの具体例って面白いですよね
「人を動かす」を読んだ感想
ハウツー本ではない
この本で書かれている内容は人間関係をよりよく構築し、仕事はもちろんプライベートを充実させるために応用できます。
ただ、それを小手先のテクニックとして身につけるのは少し違うと思います。
読むにあたり、気をつけていただきたポイントは「ハウツー本ではない」ということです。



人を動かすにはこうすればいいんか!!よし、やったろか〜
となってしまいがちなんですが、ちょっと待ってください。
自分の本心ではないけれど、人心掌握の手段として本書に書かれている原則を原則を応用していくと、逆にとても薄っぺらな人間関係になってしまう気がします。
読むスタンスとしては、「こうすればいいんだ」ではなく「こうすることが大事なんだ」がおすすめです。
例えを交えて説明してみます。
まずほめる
出典:人を動かす
「人を変える九原則」に書かれている言葉です。
これをテクニックとして理解した人が実践したとしてもある程度の効果はあるでしょう。
いわゆるお世辞というやつです。
でも本心からの言葉でない場合、それなりの相手には完全に見透かされてしまいます。
おだてててきやがって、、、と逆効果になることすらあるのです。
重要なことは「まずほめる」ことではなくて、その行為が好意的な印象につながる理由を理解することです。
本書はそういった目線で読み進めていくと、非常に勉強になることが多いです。
人って面白いなーって素直に思いますね。
まとめ:「人を動かす」というが、結局「動くのは自分」
最後にまとめです。
「人を動かす」というタイトルを見て、動くのは相手だと思いがちですがそうではありません。
結局、まず行動を変えるのは自分自身です。
ただ全部自分でやるというわけではなく、自分が変わることで初めて相手の変化を期待できるということ。
これが一番大切なポイントだと思いました。
良好な人間関係に万能薬はなく、試行錯誤しながらせいぜいもがき苦しめとカーネギー師匠から囁かれている気がします。
余談ですが、著者であるカーネギーさんは日本に旅行に訪れたことがあるそうです。
「日本で一番印象深かったものは?」という質問に「日本人です」と言い残したとのこと。
いや、そこじゃねーよ、、、とツッコミたくなる気持ちをグッと堪えて、人間への関心力を強めていきたいものですね。
最後までお読みいただきありがとうございました!
気になった人はぜひ本書を手に取ってみてください♪
それじゃ、またね!!


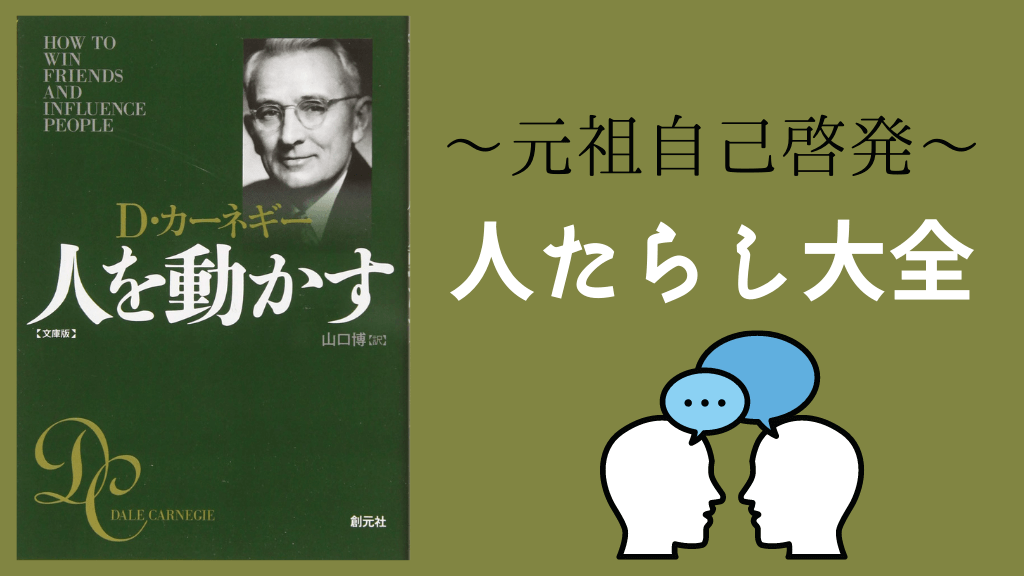
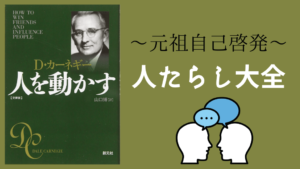
コメント